
文系出身の僕が、第二種電気工事士試験に合格するまでに掛かった費用や、勉強時間をまとめたので紹介します。
理系・文系関係なく、努力さえすれば合格できるところが第二種電気工事士の良いところなので、今後、第二種電気工事士試験を目指す方の参考になればと思います。
資格を取得して良かったこと
- 電気の基礎的な知識を身に着けることができた
- キャリアアップにつながった(会社から評価された)
- 幅広く需要のある資格なので、電気工事系やビルメンテナンス等の異業種への転職の道についても開くことができた
取得しようと思った理由
仕事で電気に関する知識が必要だった
システムエンジニアはプログラミングやパソコンで設計書を作っているイメージがあるかもしれませんが、実際にはサーバーの選定や搬入などの仕事も担当します。
その際に、データセンターや顧客先に対して必要な電力を説明したり、電源ケーブル等の確保・準備も必要です。
場合によっては工事等も必要になり、工事担当者との会話も必要になるため、電気についての基礎知識が必要でした。
キャリアアップのため
仕事を辞めた際の転職に有利になると思ったからです。
システムエンジニアという仕事は、みなさんの思っている通りキツイ仕事で、常に新しい技術が登場するため、勉強が必要になる業界でもあります。
そんな生活に耐えられなくなる日もくると思い、何かあっても転職できるように準備しておきたいと思ったからです。
DIYに興味があった
第二種電気工事士の資格を取得することにより、家庭のコンセント交換や配線等が可能になります。(無資格ではできません。)
今後、家を購入した際に自分でコンセントの増設をしてみたいと思ったからです。
勉強時間
取得するのに掛かった勉強時時間については、個人差があるため正確なことは言えませんが、文系学部出身の電気知識皆無の素人が、取得するために掛かった勉強時間を記載するので参考にしてください。
第二種電気工事士の試験は、学科と実技で試験内容が分かれているため、分けて紹介します。
ポイント
試験日は別日になっており、実技試験は学科試験の約1カ月後に実施されます
学科試験
学科試験の勉強時間については、だいたい試験日の2カ月前から勉強を始めて平均毎日2時間を費やしたので、120時間ほど勉強しました。
最初に始めた勉強ですが、まずは参考書を意味が分からなくてもよいからとりあえず読み込み、どこに何が書いてあるについて、分かるようにしました。(2周目くらいで、分かるようになりました。)
その状態で前回の過去問を1回解いたら、点数は38点だったため、間違った個所について答えを確認し、参考書を使って理解を深める作業を淡々とやっていった結果、合格点を取れるようになりました。
個人的な感想ですが、参考書をきっちり読み込む勉強をしてしまうと時間が掛かるため、トライ&エラーの精神で最初に参考書を軽く読んでから、ガンガン過去問をやった方が効率が高いと思います。
使用した参考書は「ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士筆記試験すい~っと合格」で、ネット等で検索した結果一番評価が良かったので選びましたが、図を使用した解説が多いため、イメージで理解することができたので、分かりやすかったです。
学科試験に使用した参考書はこれのみで、他は不要でした。
実技試験
実技試験の試験内容は、与えられた時間内に課題を作成する内容のため、学科試験の合格が決まってから勉強を開始しました。
まず僕が始めたことは、実技試験はどんなことをするのかのイメージを持つためにYoutubuで実技試験のイメージを掴み、3日間ほど(6時間)結線図の作成練習をしました。
ポイント
出題のパターンがすでに発表されているため、そこまで難しくはなく、3日間あれば結線図を作成できるようになると思います。
その後は工具の使い方や作成方法を習得するために、3日間ひたすら皮むきや圧着等の練習を繰り返し、ある程度慣れてきたら、本番を想定して毎日一回は時間を計測しながら課題を作成する練習をしました。
試験日一週間前になればある程度作成できるようになっていると思うので、細かいところでミスをしないように参考書等に記載されている注意ポイントを確認し、当日までに万全の状態に仕上げました。
実際に勉強で使用した参考書は学科試験の時と同じシリーズの「ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 技能試験すい~っと合格」です。
丁寧な説明で写真付きの解説があり、DVDも付属しているため、実際に動画で作業手順を見ることでさらに理解を深めることができるようになっているのでお勧めです。
合格発表から申請まで
技能試験から約1カ月後にWEBサイトで、合格発表が行われます。
技能試験を実施した日から合格発表の日まで、落ち着かない気持ちで一杯でしたが、合否のWEBサイトに自分の受験番号が表示されていた時は嬉しかったです。
合格発表から2日程して、合格通知書が送られてきました。
この合格通知書は各都道府県に対して、第二種電気工事士の登録をする際に必要な物になり、登録をしなければ実際の工事はできません。
今現在のところ、申請期限などはありませんが、いつ制度が変更になるか分からないので、早めに登録はしておいた方がよいと思います。
登録をするために必要な物は以下です。
登録に必要な物
- 各都道府県の証紙(5200円)
- 住民票
- 合格通知書
- 登録に必要な申請書
- 返信用の封筒
- 証明写真
詳細に関しては、各都道府県のWEBサイトは参照ください。
各都道府県の組合に対して申請書を送付してから、10日程で免状(資格証明書)が送られてきましたが、合格発表直後などは時間がかかる場合があるようです。
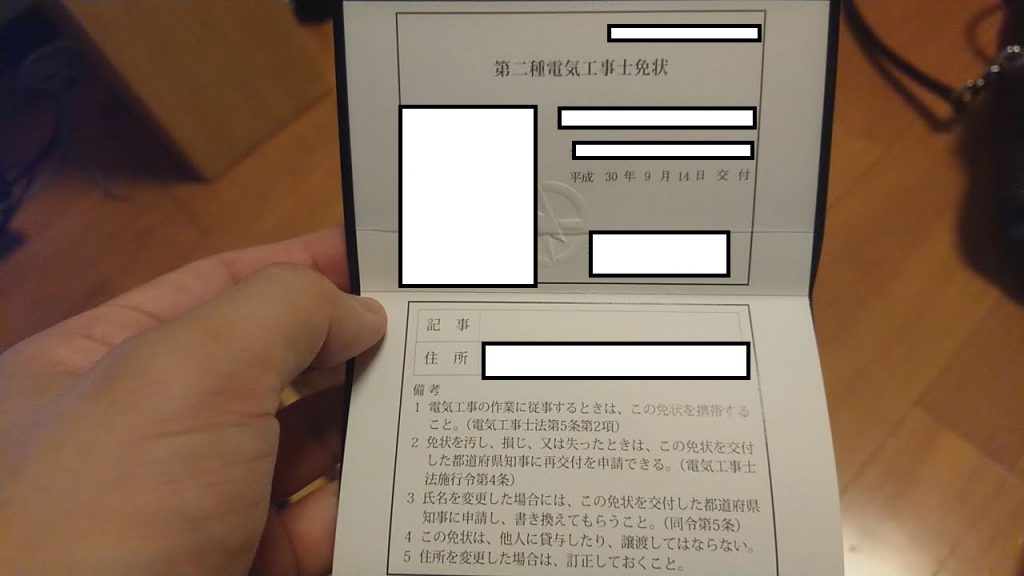
取得するのに掛かった費用
第二種電気工事士の資格を取得するためにかけた費用の総額は以下です。
参考書代
学科試験と実技試験の2冊分を購入しました。
金額
2000円×2冊=4000円
実技試験で費用な工具
実技試験で必要な工具を購入した金額です。
メルカリやヤフオク!等を活用すれば安く購入できますが、試験中の故障等のリスクを考えると新品を購入した方が良いです。
金額
14000円
実技試験の練習で必要な機材
自宅で実技試験の練習をするために必要なコンセントやケーブル等の機材です。
練習用なので、メルカリやヤフオク!等で安く購入するのも有りです。
金額
15000円
試験料
他の資格試験に比べて少し高いと思いますが、学科試験と実技試験の2回分の人件費や場所代、実技試験の機材等を考えると妥当な金額だと思います。
金額
9300円
電気工事士の登録費
住民票のある各都道府県に対して申請をしなければ電気工事になることができません。
運転免許にあるような更新費用は発生しません。
金額
5200円
合計金額
僕はすべての機材を新品でそろえてしまったため、上記のような金額になっていますが、中古を活用すればもう少し値段を抑えることができます。
金額
合計金額:47500円
まとめ
僕は文系学部出身で、理系の勉強はほとんどしてきませんでしたが、参考書を購入して分からないことを一つ一つ解決した結果、合格することができました。
実際に取得するまでに時間や費用は結構掛かってしまいましたが、僕にとってはいい経験になったと思います。
第二種電気工事士試験は、誰でも勉強すれば取得できる資格だと思うので、興味がある方はチャレンジしてみてください。



